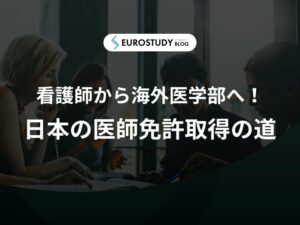海外医学部生向け、第119回医師国家試験結果の「認定」と「予備試験」区分を徹底分析!
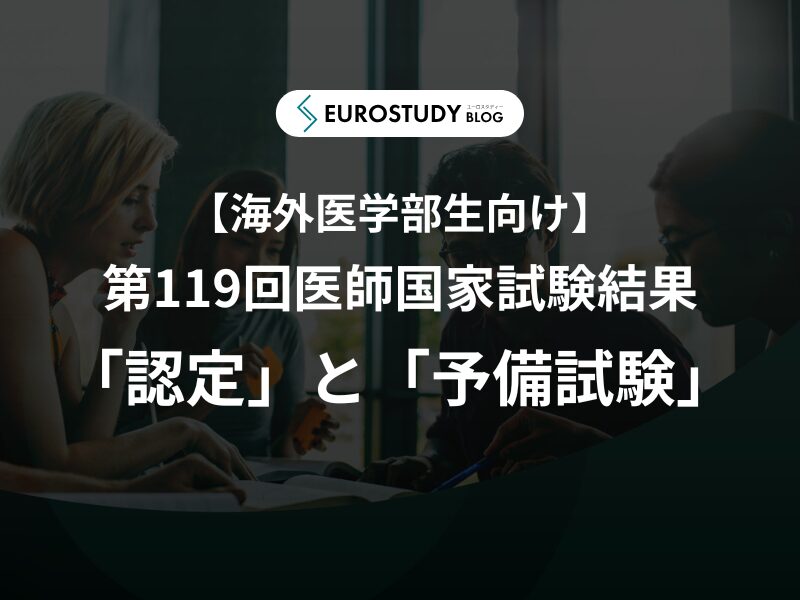
はじめに
こんにちは、医学生や医師国家試験に関心のある皆さん!今回は、2025年3月14日に合格発表が行われた第119回医師国家試験のデータを基に、「認定」と「予備試験」という2つの受験資格区分について分析してみました。この試験は、2025年2月8日・9日に実施され、医師を目指す多くの受験生が挑戦した重要な試験です。では、早速データを見ていきましょう!
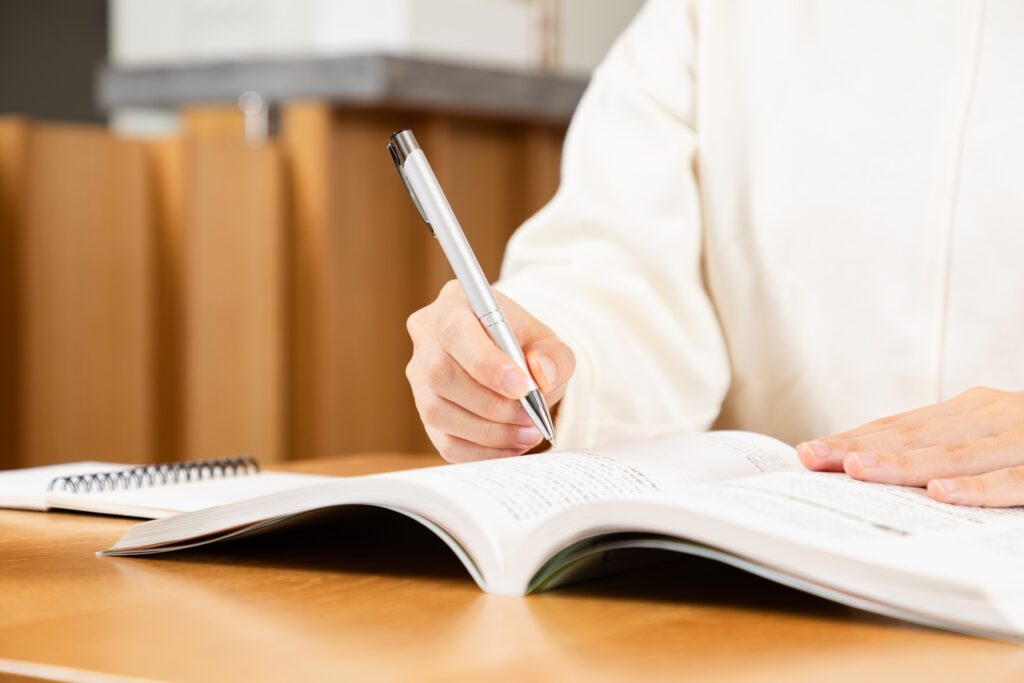
データ概要
以下は、「認定」と「予備試験」の区分ごとの受験者数、合格者数、そして合格率の詳細です。
1.「認定」区分
- 全体
- 出願者数: 291人
- 受験者数: 286人
- 合格者数: 149人
- 合格率: 52.1%
- 新卒
- 出願者数: 169人
- 受験者数: 168人
- 合格者数: 96人
- 合格率: 57.1%
- 既卒
- 出願者数: 122人
- 受験者数: 118人
- 合格者数: 53人
- 合格率: 44.9%
2.「予備試験」区分
- 全体
- 出願者数: 33人
- 受験者数: 33人
- 合格者数: 23人
- 合格率: 69.7%
- 新卒
- 出願者数: 23人
- 受験者数: 23人
- 合格者数: 18人
- 合格率: 78.3%
- 既卒
- 出願者数: 10人
- 受験者数: 10人
- 合格者数: 5人
- 合格率: 50.0%
分析ポイント
1. 受験者数と合格率の比較
まず目を引くのは、「認定」区分と「予備試験」区分の受験者数の差です。「認定」区分の受験者数は286人と、「予備試験」区分の33人に比べて圧倒的に多いですね。これは、「認定」区分が主に医学部を卒業した受験生を対象としているのに対し、「予備試験」区分は医師国家試験予備試験に合格し、実地修練を経た少数の受験生に限られております。
合格率を見ると、「予備試験」区分全体の69.7%が「認定」区分の52.1%を大きく上回っています。この差は、予備試験を経た受験生が厳しい選抜をすでに通過していることや、実地修練による実践的な知識が試験に活かされている可能性を示唆しています。
2. 新卒と既卒の違い
次に、新卒と既卒の合格率に注目してみましょう。
「認定」区分
新卒の合格率57.1%に対し、既卒は44.9%と約12ポイント低い結果に。新卒の方が試験対策を直近で集中的に行える環境にあることが影響しているのかもしれません。一方、既卒は受験者数118人中53人が合格しており、一定の合格者を輩出しているものの、準備期間の長さやモチベーション維持の難しさが合格率に響いている可能性があります。
「予備試験」区分
こちらは新卒の合格率が78.3%と非常に高く、既卒の50.0%を大きく上回っています。特に新卒の受験者23人中18人が合格している点は注目に値します。予備試験合格後の実地修練を終えたばかりの新卒生は、知識も実践力もフレッシュな状態で試験に臨めたのでしょう。一方、既卒は受験者10人中5人と小規模ながら、合格率50.0%は奮闘の跡が見られます。
3. 出願者数と受験者数の乖離
「認定」区分では、出願者数と受験者数に若干の差があります(全体で291人→286人、新卒で169人→168人、既卒で122人→118人)。これは、試験直前に棄権した人がいたことを示しています。一方、「予備試験」区分では出願者数と受験者数が完全に一致しており、全員が試験に臨んだことがわかります。受験者数が少ない分、強い決意を持って挑んだ受験生が多かったのかもしれません。
考察:試験難易度との関連は?
第119回医師国家試験は、過去の傾向から海外医学部卒業生にとってはやや難化傾向もしくは、日本人以外の受験者数が増加したことによる日本語理解の観点からの合格率低下があったと予想されます。「認定」区分の合格率52.1%は、前回の第118回(全体合格率92.3%と仮定した場合)と比べると低めです。これは、試験問題が実践的かつ骨太な出題にシフトした影響を受けた可能性があります。一方、「予備試験」区分の高い合格率は、予備試験突破からの段階的な基礎知識や応用知識の獲得と、実地修練で培った臨床的視点が功を奏した結果であることは間違いないでしょう。
予備試験から挑戦することの意義
「予備試験」区分の高い合格率を見て、予備試験からのルートで医師を目指すことの意義について考えてみましょう。
まず、医師国家試験予備試験を経て国家試験に挑戦する道があります。このルートは、世界の医科大学(医学部「5年以上(専門課程;4年以上) であり、専門科目の履修時間が3500時間以上、かつ一貫した現代西洋医学の専門教育を受けていること」)を卒業した多様なバックグラウンドをもつ医療人材を育成する上で重要な役割を果たしています。
特に注目すべきは、予備試験合格後に課される実地修練です。日本では、医師としての資質を担保するため、1年間の実地修練が必須とされています。この期間に、実際に我が国の医療現場で患者と向き合い、臨床スキルを磨くことで、机上の知識を実践に結びつける力が養われます。今回のデータで「予備試験」新卒の合格率が78.3%と高いのも、この実地修練が試験に直結する力を与えている証拠と言えるでしょう。
日本での実地修練の重要性
日本の医師養成における実地修練の重要性は、単に知識を補完するだけでなく、医師としての倫理観や責任感を育む点にもあります。患者とのコミュニケーション、チーム医療での協働、そして急変時の判断力——これらは教科書だけでは身につかず、現場での経験を通じて初めて培われるものです。「予備試験」区分の受験生が示した高い合格率は、実地修練が医師国家試験の難問に対応する力を高めていることを示しています。
一方で、「認定」区分の卒業生にとっては、実地修練の機会が与えられておらず、予備試験区分との合格率との間に大きな差が生じていると推察できます。こうした点から、海外医学部卒業者にとっては、試験前に日本の臨床現場での経験を積む工夫が重要かもしれません。
まとめ
今回の分析から、「認定」区分は受験者数が多く合格率が相対的に低いのに対し、「予備試験」区分は少人数ながら高い合格率を誇ることがわかりました。特に「予備試験」新卒の78.3%という数字は、実地修練を通じた実践力の重要性を物語っています。また、予備試験ルートは、多様な背景を持つ人が医師を目指すための貴重な道であり、日本の医療の未来に新しい風を吹き込む可能性を秘めています。
受験生の皆さんにとって、このデータが今後の試験対策やモチベーション維持の一助になれば幸いです。第119回医師国家試験を終えた皆さん、お疲れ様でした!そして、次回挑戦する方は、ぜひ実地修練の価値も意識しながら準備を進めてくださいね。
©️ 2025 宮下隼也 M.D.