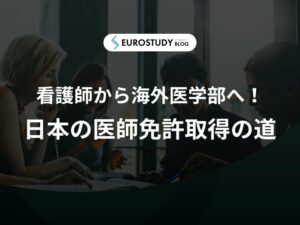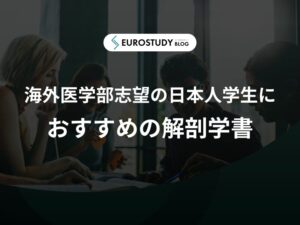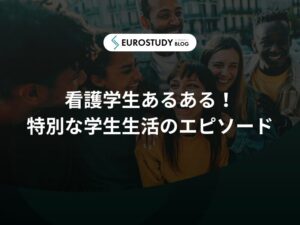看護師に臨床研修医のような「義務的な研修期間」がない理由についての考察
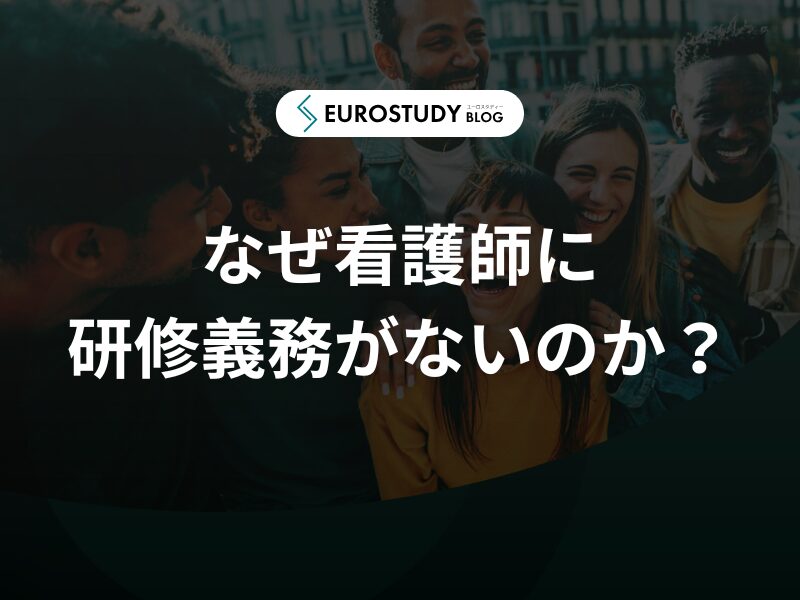
はじめに
医師と看護師では、業務範囲や現場での役割が異なりますが、この両資格、医療専門職としては最初に連想される代表的な二つなのではないでしょうか。本日は学業を修めた後に、実際に現場に出た直後から開始される新人への教育システムの違いについて、特に看護の立場から考えていきたいと思います。実際に当該資格を修めようと学校に通った後にはどのような研修が待っているのか、ざっとではありますが両者の違いに着目をしながら見ていきましょう。

医師と看護師の養成過程の相違について
医師は、大学医学部で6年間学んだ後、国家試験に合格して免許を取得しますが、その直後に「初期臨床研修医」として2年間の義務的な卒後臨床研修(初期研修)を受けることが法律により定められています。これは、医師として独立して診療行為を行うために必要な幅広い臨床能力を身につけるためです。医学生の多くは、医学部の最高学年在学中、マッチングと呼ばれる段階を経て、将来の自身の進路希望や理想の学習環境を獲得できるように研修病院を選択していきます。ただし、医学部への入学に際して地域枠や診療科指定入学枠といった条件の課された入学試験を受験し、それに合格しての医学生生活であった場合には、自身の希望を検討するにあたり、ある程度の制約が課される可能性も視野に入れておきましょう。医師は初期研修を2年間終えた後、いよいよ自身の希望の診療科の専修的な学習に進み、3年間の「後期研修医」としての働き方が始まることになります。
対して看護師は、看護系大学や専門学校での3-4年間の学びを経た後に、国家試験に合格すれば直ちに看護師としての就業が可能です。医師の研修医期間とは異なり、卒後の「義務的な」臨床研修期間は法的には一切設けられていません。とはいえ、一般的には多くの医療機関において、新人看護師研修は新卒で病院に看護師として採用されてからおおよそ1年間、初年度の全ての月に渡って(4月採用ならば大抵は翌3月まで)段階的に実施されることになりますが、これらの教育の具体的なプログラム内容や持続期間は、各施設や法人毎に異なるものであることは確かです(医師の世界ほど、横並びには統一されていません)。
看護師の卒後研修の現状
2009年の法改正により、看護師も「免許取得後に臨床研修等を受け、その資質の向上に努めなければならない」と積極性のある生涯学習の必要性と専門性向上の重要性が明記されるようになりましたが、未だ医師のような「義務化」ではなく、「努力義務」とされています。
ただし、実際には多くの医療機関で新人看護職員研修(OJT形式のものや全体での集合研修、オンライン研修や看護技術データベースの活用など、方法は多岐に渡ります)が、制度化されている場合が殆どであり、1年目の時期に基礎的な実践能力を身につけるプログラムが整備されています。
しかしながら、これらは各施設の裁量に委ねられており全国一律の義務的な臨床研修制度ではないことに今一度注意が必要となります。
義務的な臨床研修期間がない背景
a. 業務範囲・責任の違い
医師の場合には現場における診断・治療の最終責任者(そして最終判断の当事者)となる可能性が濃厚であり、診療行為の独立性が非常に高いため、卒後早めに独り立ちできるための臨床能力の獲得が必要不可欠です。そのため、国家資格取得後にも一定期間の臨床研修(初期2年後期3年)が義務付けられています。
看護師は、医師の指示のもとで患者ケアを行う役割が中心であり、チーム医療の中で段階的に実践力を高めていくことが必要とされています。医師と看護師の間にヒエラルキーのような概念は存在しませんが、医師のように一定期間集中的に学ぶというよりは、業務範囲が兎に角広範であるがゆえに、現場でのOJTや先輩看護師からの指導のもとで、実践力を身につける文化が根付いています。特に日本の医療現場では指導者をプリセプター、指導対象者をプリセプティと呼ぶ慣習があります。新卒者は体系立ったプリセプターの指導のもと、患者さんにとって安全で安楽な看護手技の実施ができるようになっていきます。
b. 医療現場の人員配置・即戦力化の要請
現在、本邦の医療現場では慢性的な看護師不足が続いており、新人看護師を即戦力として現場に配置するニーズが益々高まっている状況です。そのため、免許取得後はすぐに現場で働きながらOJTで育成する体制が今や主流となっています。
c. 制度化の難しさと多様な現場ニーズ
医療機関の規模や機能、地域性により、必要とされる看護実践能力や研修内容が実際には大きく異なることが、医師ではなく看護師の職務内容の特徴といえます。医師は初期研修では横並びに全国誰でも同じ内容を身につけ、それらを確固とした基礎としてから後期研修で初めて専門別に分かれていきますが、看護師に関しては勤める職場やその現場が扱う医療の性格によって、身につけるべき業務内容が変わってくるからです。そのため、医師のような全国一律の義務的な臨床研修制度の導入は、我が国の看護協会が長年検討に加えてきた内容では有りながらも、あくまで理想論に留まっているような現状があり、看護師の働くことのできる現場の多様性や、フレキシブルな人材配置を望む現場との乖離がある、といった意見もあります。
近年の動向と今後の課題
新人看護職員研修は、法律上の努力義務となり、多くの医療機関では創意工夫に満ちたプログラム作成と、その内容の充実が図られています。厚生労働省のガイドラインでは、1年以内に基本的な臨床実践能力の修得を目標とし、その上で更には院内外での研修や多施設/多職種での合同研修も行うなど、各人材の能力開発にあたっての多様かつユニークな試みが見られます。
一方で、「新人看護師の早期離職防止」「看護の質の向上」「医療安全の確保」の観点から、より体系的な卒後研修の必要性も長年指摘され続けてます。海外では、ベトナムのように看護師に対する卒後臨床研修を義務化する国もあり、日本でも今後制度のあり方が議論され続ける可能性があります。
結論
看護師に医師のような義務的な臨床研修期間がないのは、業務範囲の違い、現場の人員配置の実情、制度化の難しさなどが背景にあります。しかし臨床研修期間が正式には存在しないながらも、実際には多くの医療機関において新人看護職員研修が入職直後の一年間を目安に行われており、それらが、医師にとってのちょうど初期研修医のような期間だと対照的に考えることも可能です。患者さんのニーズに常に応える高レベルなチーム医療を展開していくためには、医師の世界のように研修システムを制度化していくことも一つの解決策として考えられます。いずれにせよ、日本では今後も看護の質向上のために対看護師卒後教育の更なる充実が喫緊に求められています。
©️ 2025 株式会社EUROSTUDY