高校生のための有機化学 – 基礎講座Ⅰ

目次
はじめに
海外医学部、特に欧州の医学部を目指す高校生向け(全受験生向け)に、化学の基礎的な概念を簡潔にまとめました。医学部入試で問われる重要な化学の基礎知識を効率的に学習できるよう構成されています。
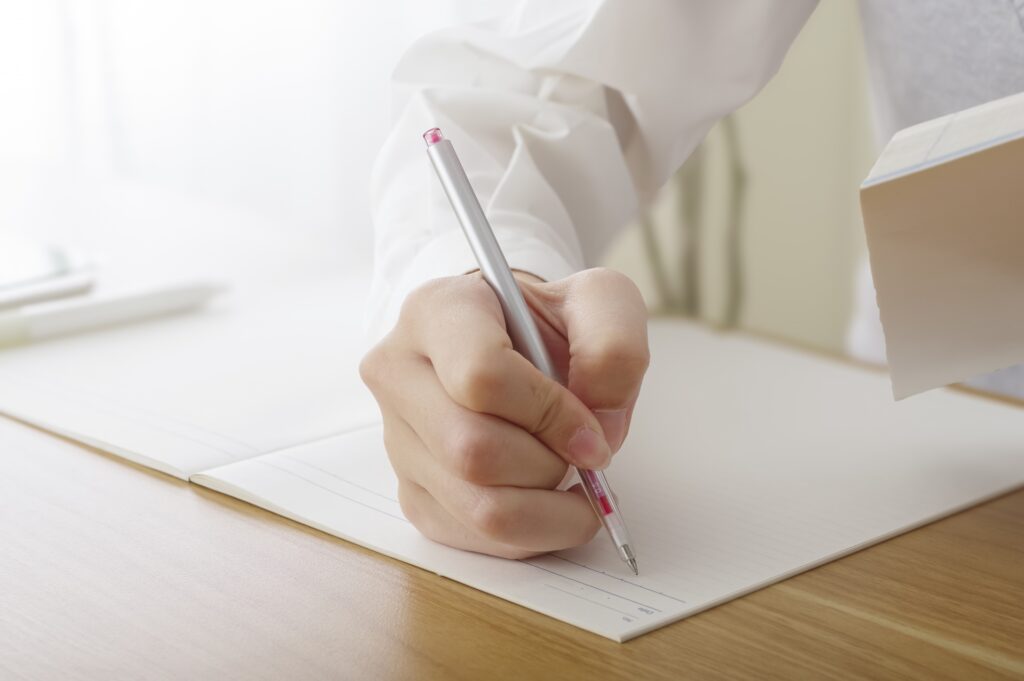
1.原子構造
1.1 原子の基本構造
原子は物質の基本的な構成単位であり、それ以上分割できない最小の粒子と考えられていました。しかし現代の科学では、原子はさらに小さな粒子から構成されていることがわかっています。
原子の主な構成要素
- 陽子(Proton)
- 正の電荷(+1)を持つ
- 原子核に存在する
- 質量:約1.67 × 10^-27 kg(1 amu)
- 原子番号を決定する
- 中性子(Neutron)
- 電荷を持たない(中性)
- 原子核に存在する
- 質量:約1.67 × 10^-27 kg(1 amu)
- 同位体の違いを生む
- 電子(Electron)
- 負の電荷(-1)を持つ
- 原子核の周りを軌道運動する
- 質量:約9.11 × 10^-31 kg(陽子の約1/1836)
- 化学反応や結合に関与する
重要な概念
- 原子番号(Atomic Number, Z): 原子核内の陽子の数
- 質量数(Mass Number, A): 陽子と中性子の合計数
- 同位体(Isotope): 同じ元素で中性子の数が異なる原子
- イオン(Ion): 電子を失ったり獲得したりして電荷を持った原子
1.2 電子配置
電子は原子核の周りをランダムに動き回っているのではなく、特定のエネルギー準位(殻)に配置されています。
電子殻とエネルギー準位
- 主量子数(n): 1, 2, 3, 4, … (K殻, L殻, M殻, N殻, …)
- 各殻の最大電子数: 2n²
- K殻(n=1): 最大2電子
- L殻(n=2): 最大8電子
- M殻(n=3): 最大18電子
- N殻(n=4): 最大32電子
電子配置の表記法
- オービタル表記:1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶, …
- s軌道: 各主量子数につき1個(最大2電子)
- p軌道: 各主量子数(n≧2)につき3個(最大6電子)
- d軌道: 各主量子数(n≧3)につき5個(最大10電子)
- f軌道: 各主量子数(n≧4)につき7個(最大14電子)
例)
- 水素(H): 1s¹
- ヘリウム(He): 1s²
- リチウム(Li): 1s² 2s¹
- 炭素(C): 1s² 2s² 2p²
- 酸素(O): 1s² 2s² 2p⁴
- ナトリウム(Na): 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹
フントの規則と禁止原理
- パウリの禁止原理: 同じ原子内で、4つの量子数が全て同じ電子は存在できない
- フントの規則: 同じエネルギー準位のオービタルには、まず一つずつ電子が入る(平行スピン)
練習問題
- 酸素原子の陽子数、中性子数、電子数はそれぞれいくつですか?
- マグネシウム(Mg)の電子配置を書いてください。
- カルシウムイオン(Ca²⁺)の電子配置はどうなりますか?
2.周期律と元素の周期表
2.1 周期表の構造
周期表は、元素を原子番号順に並べ、化学的性質の類似性に基づいて配置したものです。
周期表の基本構成
- 周期(Period): 横の行(全7周期)
- 各周期は新しい電子殻から始まる
- 族(Group): 縦の列(全18族)
- 同じ族の元素は類似した化学的性質を持つ
- 主な族
- 1族: アルカリ金属(Li, Na, K, …)
- 2族: アルカリ土類金属(Be, Mg, Ca, …)
- 17族: ハロゲン(F, Cl, Br, …)
- 18族: 希ガス(He, Ne, Ar, …)
- ブロック
- s-ブロック(1, 2族)
- p-ブロック(13-18族)
- d-ブロック(3-12族、遷移元素)
- f-ブロック(ランタノイド、アクチノイド)
2.2 周期的傾向
原子半径
- 周期内: 左から右へ減少する
- 理由)原子番号が増加するにつれて核電荷が増加するため、電子は核に引き寄せられる
- 族内: 上から下へ増加する
- 理由)新しい電子殻が追加されるため
イオン化エネルギー
- 定義: 気体状態の原子から電子を1つ取り除くのに必要なエネルギー
- 周期内: 左から右へ増加する 例外: Be→B, N→O など
- 族内: 上から下へ減少する 例外: 一部の遷移元素など
電気陰性度
- 定義: 原子が化学結合において電子を引き付ける能力
- 周期内: 左から右へ増加する
- 族内: 上から下へ減少する
- 最も電気陰性度が高い元素: フッ素(F)
金属性・非金属性
- 金属: 周期表の左側と中央
- 特徴)電子を失いやすい、光沢がある、電気・熱の良導体
- 非金属: 周期表の右上
- 特徴)電子を獲得しやすい、絶縁体が多い
- 半金属(metalloid): 金属と非金属の境界 例)B, Si, Ge, As, Sb, Te
練習問題
- 周期表において、原子半径が最も大きい元素はどこに位置する傾向がありますか?
- フッ素(F)とヨウ素(I)では、どちらの電気陰性度が高いですか?その理由も説明してください。
- なぜアルカリ金属(1族)は反応性が高いのですか?
3.化学結合
3.1 結合の基本概念
化学結合は、原子が安定なオクテット構造(外殻に8個の電子)を形成しようとする傾向から生じます。これはオクテット則として知られています。
結合の主な種類
- イオン結合: 電子の完全な移動
- 共有結合: 電子の共有
- 金属結合: 自由電子の共有
- 水素結合: 水素原子を介した分子間の弱い結合
- ファンデルワールス力: 分子間の非常に弱い引力
3.2 イオン結合
イオン結合は、一方の原子から他方の原子へ電子が完全に移動することで形成されます。
特徴
- 金属元素と非金属元素の間で形成されることが多い
- 電子を失った原子は陽イオンに、電子を獲得した原子は陰イオンになる
- イオン間の静電引力により結合が形成される 例)NaCl(塩化ナトリウム)
イオン結晶の性質
- 高い融点・沸点
- 固体状態では電気を通さないが、水溶液または溶融状態では電気を通す
- 多くは水に溶けやすい
- 硬くて脆い
3.3 共有結合
共有結合は、原子間で電子対を共有することで形成されます。
特徴
- 主に非金属元素間で形成される
- 1つの結合につき1対の電子を共有する 例)H₂, O₂, CH₄
共有結合の種類
- 単結合: 1対の電子を共有(H-H)
- 二重結合: 2対の電子を共有(O=O)
- 三重結合: 3対の電子を共有(N≡N)
極性と非極性共有結合
- 非極性共有結合: 電子対が等しく共有される(同じ元素間など) 例)H₂, Cl₂, O₂
- 極性共有結合: 電気陰性度の差により電子対が不均等に共有される 例)H₂O, NH₃, HCl
分子の形状(VSEPR理論)
電子対反発理論(VSEPR)によると、原子価殻電子対は互いに反発し、できるだけ離れた配置を取ります。
<主な分子形状>
- 直線型: BeCl₂(2つの電子対)
- 平面三角形: BF₃(3つの電子対)
- 四面体: CH₄(4つの電子対)
- 折れ線型: H₂O(4つの電子対、うち2つは非結合電子対)
- 三角錐形: NH₃(4つの電子対、うち1つは非結合電子対)
3.4 金属結合
金属結合は、正の電荷を持つ金属イオンが「電子の海」と呼ばれる自由電子によって結びついた結合です。
特徴
- 金属元素間で形成される
- 価電子は特定の原子に局在せず、自由に動き回る 例)Fe, Cu, Al
金属の性質
- 電気・熱の良導体
- 展性・延性に優れる(形を変えやすい)
- 光沢がある
- 多くは高い融点・沸点を持つ
練習問題
- 次の化合物の結合の種類を特定してください:MgO, CO₂, Fe
- H₂O分子の形状と結合角について説明してください。
- なぜNaClは固体状態では電気を通さず、水溶液中では電気を通すのですか?
総合演習問題
1.炭素原子(C)の電子配置を書き、価電子数を答えなさい。
2.次の元素について、周期表上の位置(周期と族)を示しなさい。
- a) カリウム(K)
- b) 塩素(Cl)
- c) マグネシウム(Mg)
3.周期表において、原子半径とイオン化エネルギーの傾向を説明しなさい。
4.次の分子の結合の種類と分子形状を予測しなさい。
- a) CO₂
- b) NH₃
- c) CH₄
5.次の反応における電子の移動を説明しなさい。
Ca + Cl₂ → CaCl₂
6.なぜ貴ガス(18族)は化学的に不活性なのかを電子配置の観点から説明しなさい。
付録:医学部入試によく出る重要ポイント
- 原子構造と周期表の関係
- 価電子数と族の関係
- 電子配置と元素の性質の関連
- 結合の種類と物質の性質
- イオン結合と共有結合の違い
- 結合の極性と分子の極性の関係
- 水素結合と生体分子(DNA, タンパク質)の構造
- 化学計算の基礎
- モル概念
- 化学反応式の量的関係
- 溶液の濃度計算
- 生体関連物質への応用
- 糖、脂質、タンパク質、核酸の基本構造
- 機能性官能基と生理活性
参考文献と推奨教材
- 「化学の新研究」(三省堂)
- 「理系のための基礎化学」(化学同人)
- 「Chemistry: The Central Science」(Pearson)
各大学の入試要項を確認し、必要に応じて内容を補強してください。










